この記事は下記の方にお勧めです。
・地震による家具の転倒防止対策をしたい方
・耐震試験について知りたい方
・転倒防止グッズの効果に不安のある方
はじめに
家具の地震対策をしたいけど、いろいろな商品があってどれを選んだらいいのか悩んでいたり、本当に効果があるのか疑問に思っていたりする方は多いのではないでしょうか。
本当に効果があるのかないのかは、転倒防止グッズを購入、設置して地震を経験しなくては実際のところわかりません(もちろん、経験しないのがベストです)。それは、場所によって地震の波形や大きさが異なること、建物によって揺れ方が異なること、家具の大きさや重さが異なること、床や壁の強度や材質が異なること、転倒防止グッズがきちんと設置できているかどうか、など、いろいろな条件があるからです。
一方、多くの商品には「震度7対応」とか「震度6強対応」などと書かれていることもあります。このような記載は商品を選択する上での情報になりますが、どのような基準で書かれているかがわからないこともあります。
この記事では転倒防止グッズの性能に関わる耐震試験についてまとめます。

耐震試験
耐震試験とは
耐震試験とは地震に対する商品の耐久性や安全性を評価する試験のことで、加振台を使用して行います。加振台には一軸振動装置と三軸振動装置があり、一軸振動装置は一方向のみの揺れ(前後だけ、もしくは左右だけ)で、三軸振動装置は前後左右上下に揺れます。なお、実際の地震はあらゆる方向に揺れるので、一軸の揺れではなく、三軸の揺れです。
一般的には三軸振動装置に阪神・淡路大震災や東日本大震災などの地震波形を入力することにより実際の地震を模擬した揺れでの耐震試験を行います。
振動試験装置
振動試験装置の最高峰は国立研究開発法人防災科学技術研究所 兵庫耐震工学研究センター(通称:E-ディフェンス)にあり、ここの加振台は建物を載せられるほどのスケールで、実物大の建物の試験体で耐震試験が行えます。下の写真は加振台上に建てられた体育館で、天井の落下試験を実施したときのものです。

E-ディフェンスの仕様は下表の通りです。日本最大の振動試験装置で、建物の耐震試験のためのものです。
| 震動台の大きさ Table Size | 20m x 15m | |
| 最大搭載荷重 Payload | 12MN (1200tonf) | |
| 加振方向 Shaking Direction | X, Y – Horizontal | Z – Vertical |
| 最大加速度 Max. Acceleration | 900cm/s2 | 1500cm/s2 |
| 最大速度 Max. Velocity | 200cm/s | 70cm/s |
| 最大変位 Max. Displacement | ±100cm | ±50cm |
転倒防止グッズの中にもE-ディフェンスの加振台上に設置した建物の中の部屋で家具等を固定し、振動試験が実施されたものもあります。ここで評価した商品は信頼性が高いと考えられます。
また、家具や製造設備などの耐震試験を実施できる規模の振動試験装置は、いくつかの大学や企業が所有しています。この場合、加振台の上に部屋を模擬したものを載せ、そこに家具等を設置して耐震試験を行います。下の写真は京都大学防災研究所の加振台で、下表は京都大学防災研究所の加振台の仕様です。

| テーブル | 5m( X軸方向 )×3m( Y軸方向 ) |
|---|---|
| 加振方向 | 水平2軸(X,Y)、垂直(Z)、回転( θx, θy, θz ) |
| 駆動方式 | 電気・油圧サーボ方式 |
| 継手方式 | 静圧軸受方式 |
| 最大搭載重量 | 定格15tonf、最大30tonf |
| 最大変位 | 水平(X): ±300mm 水平(Y): ±250mm 垂直(Z): ±200mm |
| 最大速度 | 水平(X): ±150cm/s 水平(Y): ±150cm/s 垂直(Z): ±150cm/s |
| 最大加速度 (15tonf戴荷時) | 水平(X): ±1G( 無負荷時±1.5G ) 水平(Y): ±1G( 無負荷時±1.5G ) 垂直(Z): ±1G( 無負荷時±1.5G ) |
| 最大回転角度 | X、Y、Z軸まわり( θx, θy, θz ): ±3° |
| 加振周波数 | DC~50Hz |
| 加振入力波形 | 正弦波、不規則波、任意波形 |
さらに、起震車で耐震試験を実施している例もあります。起震車は防災イベントなどで乗車しての地震体験をするのに使われており、起震車を見たり体験乗車したりしたことがある方もおられるのではないでしょうか?

防災イベントでは上の写真のように起震車の荷台にテーブルや椅子がセットされていることが多いですが、耐震試験をする時には荷台を空にして行います。例えば、次の動画はメーカーが公開している壁寄せスタンドの耐震試験の様子で、荷台の上に模擬テレビを取り付けた壁寄せテレビスタンドを載せて揺らせています。なお、この動画は壁寄せスタンドの耐震性能の試験で、転倒防止グッズの耐震試験ではありません。

その他にも、卓上の加振台や一軸の加振台を使用した耐震試験を行なっている例がありますが、実際の地震波とは揺れ方が全く異なるので参考程度にしかならず、この試験結果のみから「震度7対応」などと謳うのは無理があると言えるのではないでしょうか。
耐震試験の規格
転倒防止グッズの耐震試験にはJIS規格などのオーソライズされた規格がありません。したがって、転倒防止グッズのパッケージなどに記載されている「震度7での耐震試験クリア」などは、多くの場合、あくまでもその会社の独自規格での試験結果です。そのため、それぞれの会社で対象物や地震波形などの条件が異なり、「震度7クリア」と書かれている商品でも製造元が異なれば同じ性能を有しているとは限りません。
一方、公的機関である一般財団法人建材試験センターが独自の規格(東京消防庁が平成18年3月に公表した「オフィス家具・家電製品の転倒・落下防止対策に関する調査研究委員会における検討結果」に基づいた独自規格)で耐震試験を行なっています。一定の条件で耐震試験を行なっているため、一般財団法人建材試験センターの証明書を所有している商品は信頼性が高いと言えるでしょう。
どうやって商品を選択する?
耐震試験結果は商品を選択する上での大きな要素です。しかし、上記のように試験条件が統一されていないため、耐震試験結果の比較が困難です。
そこで、転倒防止グッズを選択する方法として下記をチェックしてみたらいかがでしょうか。
1.商品に耐震試験を実施したことが記載されているか?
商品のパッケージなどに「震度7対応」と記載されていても単に書いているだけかもしれません。特に輸入品などのコピー商品には注意した方が良いでしょう。「震度7対応」としか記載されていない商品を購入する前に、製造元や販売元に実際に耐震試験をしたのか、それは何処でどのような条件で実施した耐震試験なのかを問い合わせるのが良いでしょう。
2.耐震試験の実施条件が記載されているか?
どこの振動試験装置を使用したのか、どの地震の振動波形なのか、対象物は何なのかなど、できるだけ詳細な条件が記載されている方が信頼性が高くなります。また、同じタンスで試験をしても、積載物に見立てた錘をどのように積載しているかによって耐震試験結果が異なります。例えば、錘をタンスの下の方に積載すれば重心が低くなり転倒しにくくなり耐震試験結果に有利に働くので、錘の積載方法も重要です。一方、錘なしの状態での試験を行なっているようだと家具の実使用と乖離しているので試験結果に信頼性はありません。詳しい試験条件が記載されていないようであれば製造元や販売元に問い合わせるのが良いでしょう。
3.耐震試験の動画が公開されているか?
動画の内容に加えて動画の有無も判断材料になります。耐震試験は動画で見るのが最もわかりやすいですし、実際に試験を行なっているのであれば試験の様子を撮影しているのが当たり前です。逆に言えば動画がなければ試験結果を証明するものがありません。
4.耐震試験結果の証明書が公開されているか?
公的機関で行った試験だと試験結果の証明書が発行されます。これを公開している商品は第三者の試験結果なので信頼性が高いでしょう。なお、一般財団法人建材試験センターで証明された商品は下記のサイトで公開されています。
耐震試験を実施した商品は確実に安心?
残念ながら、確実に安心とは言えません。それは、転倒防止グッズが震度7での耐震試験で転倒しなかったと仮定した場合でも、下記のようなケースがあるからです。
- 特定の対象物の耐震試験しか行っていない
- 震度7には上限がない
- 地震によって、また、同じ地震でも場所によって、さらには建物によって揺れ方が異なる
- 耐震試験はその商品の取り付けのプロが取り付けている
- 耐震試験と家庭とでは床、壁、天井が異なり、耐震試験は理想的な条件で行なっている
特定の対象物の耐震試験しか行っていない
耐震試験を実施すると、1日あたり数十万円から数百万円の加振台の使用料金が必要です。また、テレビの転倒防止グッズで考えた場合、毎年、多くのメーカーからいろいろなサイズのテレビが発売されており、その種類は数百にも及びます。転倒防止グッズの会社が毎年数百種類のテレビを購入し、耐震試験を行うことは費用を考えるだけでも無理なことを理解できるのではないでしょうか。
そのため、ある特定の機種のテレビでの耐震試験結果から耐震性能を導き出すことになります。したがって、耐震試験を行なった機種のテレビだと震度7の地震で転倒しなかったとしても、それ以外の機種のテレビだと転倒する可能性がゼロとは言えません。
このことはテレビだけではなく、家具でも同じで、ありとあらゆる種類の家具の耐震試験を行うことは現実的ではありません。また、同じ家具であっても積載物の入れ方や総重量によって重心位置が変わることから、転倒のしやすさはケースバイケースになります。
震度7には上限がない
耐震試験でよく使われる地震波は阪神・淡路大震災や東日本大震災のものです。これらの地震は日本で発生した最大級の地震ですが、未来永劫にわたってこれらの地震が最大級の地震かと言えば、そうではありません。これらの地震よりも「さらに大きな」地震が発生する可能性もゼロではなく、この「さらに大きな」地震が阪神・淡路大震災や東日本大震災の数倍の大きさだったとしても震度7です。それは、震度8や震度9といった震度7以上の階級がないからです。言い換えれば、未だかつてない未曾有の規模の地震が発生しても震度7です。
つまり、耐震試験で用いた阪神・淡路大震災クラスの揺れであれば転倒しない性能を有する転倒防止グッズでも、「さらに大きな」想定外の地震では転倒する可能性があります。転倒するしないは商品の設計を阪神・淡路大震災クラスのぎりぎりにしているのか、尤度を持った設計にしているのかにより、製造元にしかわからない事項です。
地震によって、また、同じ地震でも場所によって、さらには建物によって揺れ方が異なる
上記と同じようなことですが、同じ地震でも場所が違えば揺れ方も異なります。地震計が設置されている場所よりも弱い地盤であればより大きく揺れるでしょうし、建物の構造によっても揺れ方が違ってきます。
つまり、最大震度6強の地震であっても、場所や建物によっては耐震試験を行なった阪神・淡路大震災の揺れよりも大きくあり、その場合は対象物が転倒する可能性がゼロではないということです。
耐震試験はその商品のプロが取り付けている
通常、耐震試験は製造元や販売元が主体となって実施しています。よって、耐震試験で転倒防止グッズを取り付けるのは製造元や販売元の社員で、転倒防止グッズの取り扱いに慣れたプロです。そのため、商品の取り扱い説明書に書かれていないようなノウハウを駆使して取り付けることができます。
一方、家庭で転倒防止グッズを取り付けるのは購入者です。多くの場合、初めてその商品を取り付ける、いわば素人です。取り扱い説明書を読んで、場合によっては読まずに取り付けることになりますが、もちろんノウハウなど有していないので、取り扱い説明書通りに取り付けるのが関の山です。
もちろん取り扱い説明書の出来の良し悪しにもよりますが、プロが取り付けた転倒防止グッズと素人が取り付けた転倒防止グッズとではどちらの方が転倒防止効果があるのかは考えるまでもないでしょう。
耐震試験と家庭とでは床、壁、天井が異なる
耐震試験では、地震に十分な強度のある床、壁、天井で実施します。また、耐震マットの場合だと耐震マットが十分に粘着する床にします。つまり、ある意味理想的な条件で試験を行なっています。
一方、家庭で転倒防止グッズを取り付ける場合、強度がない石膏ボードの天井に突っ張り棒を取り付けたり、耐震マットが粘着しないカーペット上に取り付けたりすることもあり得ます。このような場合、大きな地震が発生すると対象物が転倒します。
転倒防止グッズは意味がない?
そのようなことはありません。確かに、不運にも想定外の規模の地震に襲われたら転倒するかもしれませんが、想定内の地震であれば無事な可能性は高く、対策をしていなければ転倒する可能性がある震度6弱の地震に対しては効果を発揮するでしょう。
また、複数の転倒防止対策をするなどの備えをすることで想定外の地震に対しても効果を発揮する可能性もあります。
何もしなければ家具はただ倒れるだけです。少しでも被害を低減するために転倒防止対策をすることは極めて重要です。
まとめ
この記事をまとめます。



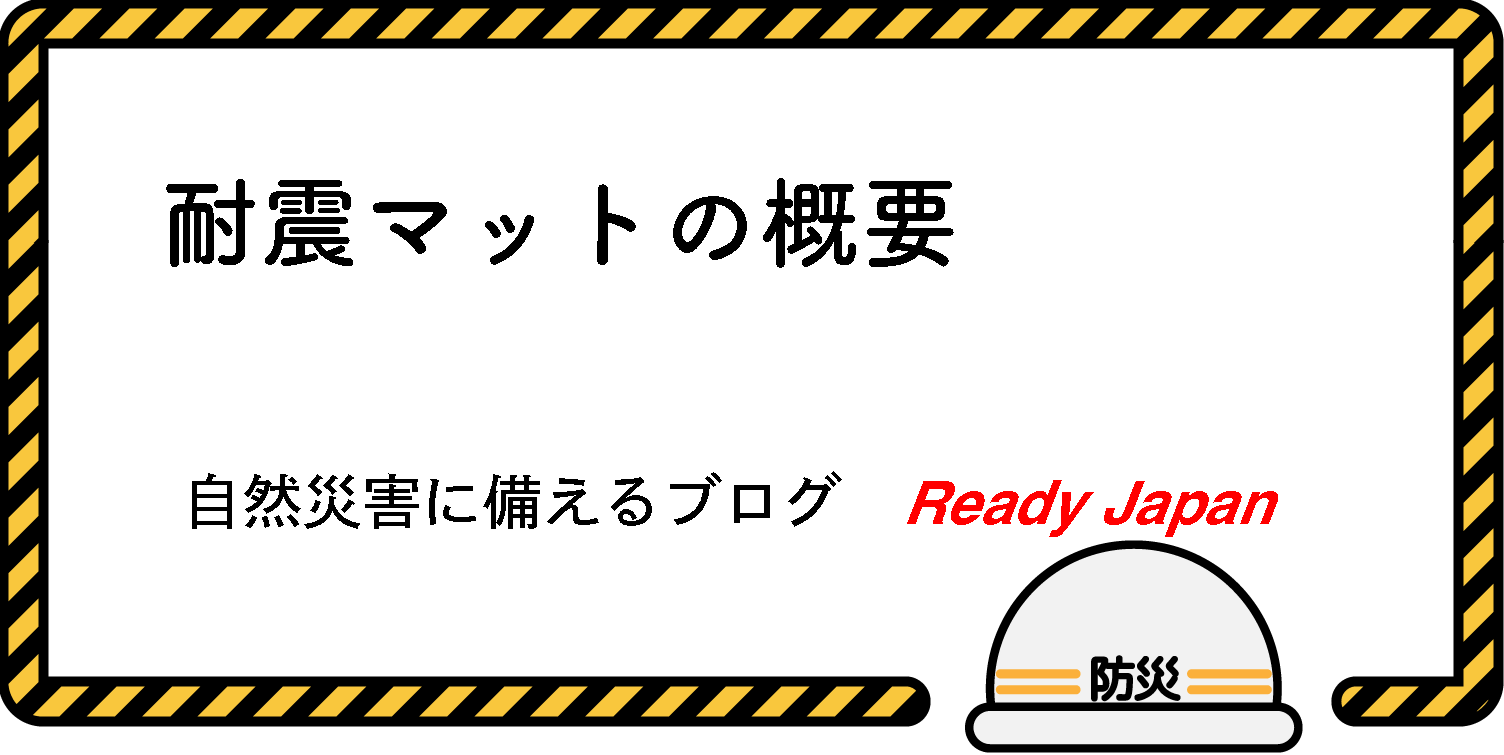
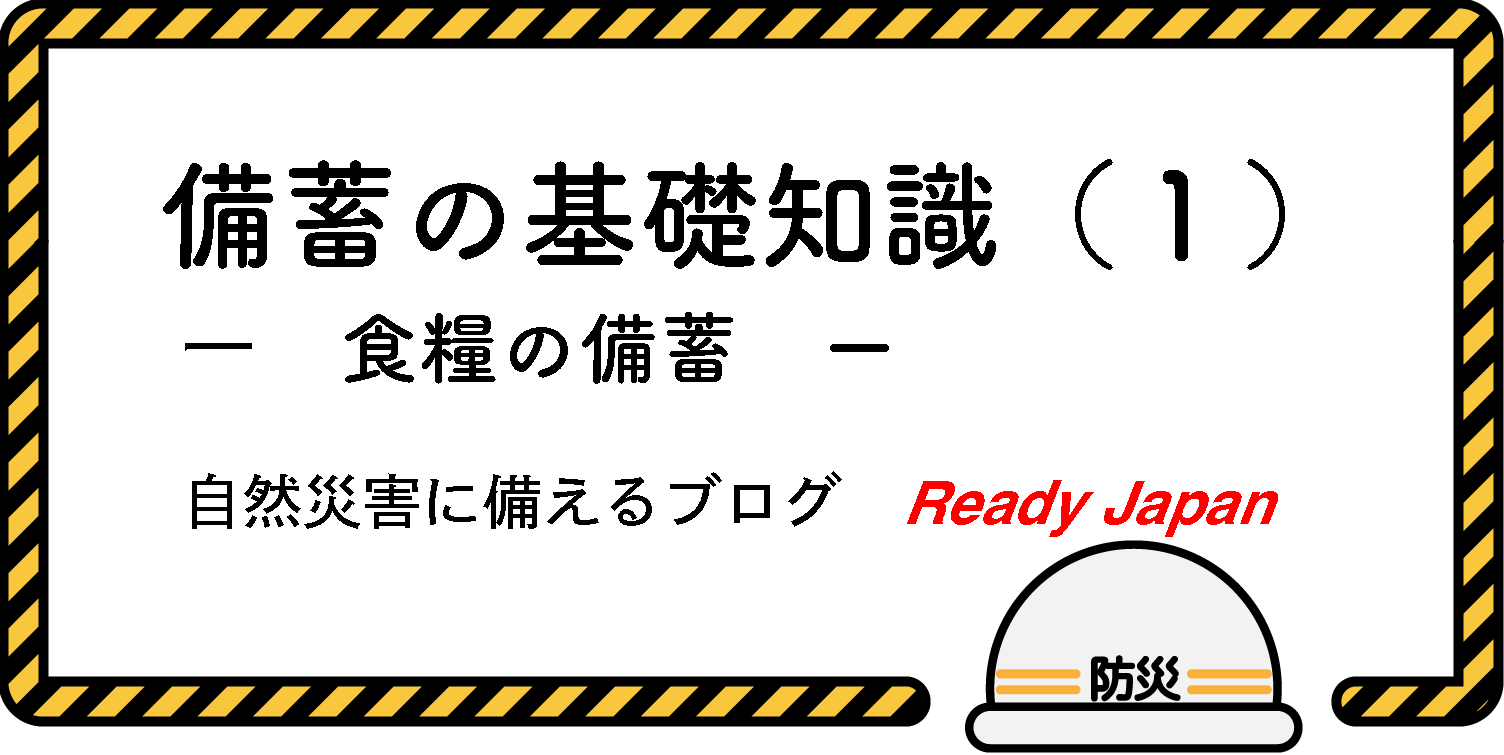
コメント